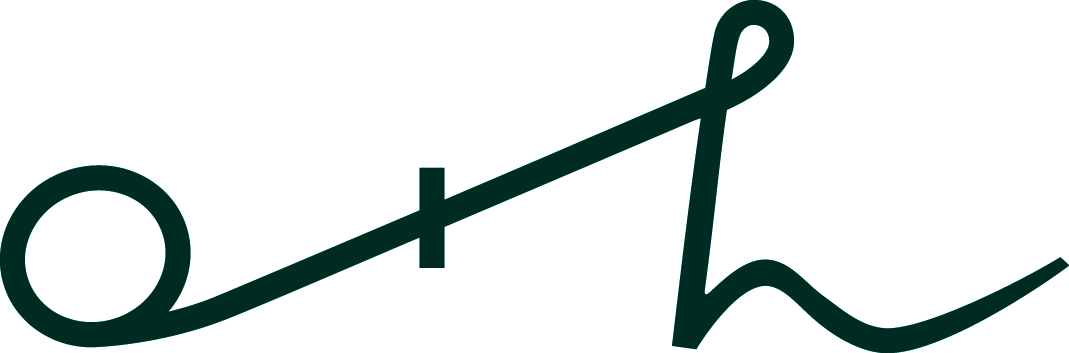「Sobrevivência」永井佳子による南米の話
2020年9月19日
17:00 プレゼンテーション
19:00 質疑・ディスカッション
イントロダクション:
Sobrevivência 「生きのびる」
ブラジルでよく聞く、ポルトガル語の単語に気になるものがあった。ソブリヴィヴェール(Sobreviver)という言葉だ。ヴィヴェール(Viver)は「生きる」という意味。Sobreがつくと、どう違うのだろう?あえて意味を確認するタイミングを逃したまま、その音を聞いて過ごしていた。だいたい、その単語が聞こえる時は、他愛もない日常の話をしている時だからだ。でも、しばらくして自然と意味がわかった。「生き延びる」ということらしい。それを聞いて愕然とした。ただ、生きる、だけではなくて、生き延びることを意識してきた人々の日常に気が付いたからだ。
永井:このプレゼンテーションはブラジルがどのようにはじまったか、ということからはじまります。最初は北東部のレシフェというところとサルバドールというところから。その二つはブラジルが始まった都市でとても文化が濃い場所です。19世紀末の奴隷解放を経て、職をもとめて北部から南部のサンパウロなどの大都市に移動してきた労働者の人々がたくさんいます。結果としてそれが大都市のホームレスの問題につながっている。最後の写真にあるのはサンパウロの9de Julho(ノヴィ・ジ・ジューリョ)というところにある施設で、MTSC(屋根のない人々のための運動)通称Ocupacao(オキュパサオン)と呼ばれている場所です。もともと電力会社の社宅だったもので、本当にサンパウロの中心部にあるのですが、ここを占拠しながらホームレスの人々が住んでいます。
私はアーティストの友人に連れられて行ったのですが、彼らはここで展覧会をしながらその建物の修繕費を稼いでいます。政府からしてみれば不法占拠、市民からしてみれば、公共施設を管理するための税金を払っているのに、政府が役割を果たしていないという言い分。実際、ここではいろいろなものが使い物にならなくて壊れています。エレベーターが使えなかったり、ガスが通っていなかったり。直さないと住めないところなのを、アーティストが展覧会をして作品を売って、その売り上げをすべて修繕資金にしています。写真に出てきた4歳の男の子はアーティストの友人の息子です。彼らは裕福なので、庭がぐるりと壁で囲まれているようなサンパウロの大きな家に住んでいるけれど、治安が悪くて危ないから壁の外で友達と遊ぶなんてことはできない。ここ(Ocupacao)ではゲートのなかに建物があるので、自由に子供たちが遊ぶことができる。団地の下で子供が遊んでいるというような状態です。ということで、うらやましくて、思わず、「ここに住みたい」と言ったのです。大西さんたちもここに行ったのですよね?
大西:ここに住むにはデモに参加したりして、一緒に戦うことがここに入る条件だと言われました。
永井:ここに集まるアーティストの人々は戦うことの一環としてボランティアの組織を組んで、資金集めをしています。ランチを振る舞うイベントをしたりして、その収益を修繕費に当てています。建築家はボランティアで建物の修繕を技術的に手伝う。アーティストが企画しているのだけど、とても組織的なんです。こういうのって、ヨーロッパとか日本だと政府から助成金をもらって、という流れになるけれど、基本的に政府は何もしてくれない。どんなレベルでも自分たちでやらなくてはいけない。
大西:永井さんが最初にブラジルにいらした時、どこへ行くかはどのように決めたのですか?
永井: 最初はアフロブラジル文化に興味があって、その中心地であるサルバドールに行きたいと思いました(10年前にはじめて行ってから、ブラジルに行く度に行っている)。だけど現地にいっても何も計画ができない。大抵、最初の2日間ぐらいをかけて現地の人々に聞き込みをする。そうすると必ず何かに遭遇するんです。(路上のサンバ・ジ・ホーダの映像をみながら)すごく若い子でもこういう場に現れて、その場にいる人がどんどん巻き込まれていくのがよいんです。現地に行くと何かがある。ここにはカポエイラのアカデミアもあります。
大西:大きい人が小さい人と対戦していましたね
永井:子供と対戦しているのが先生。60歳です。ここにいる若い子たちはみんなここで育って、今は逆に教える立場になっています。実際、シングルマザーも多い地域なので、学校帰りの時間、誰かに子供を見ていて欲しいというときにここに集まる。彼らが住んでいるところは自分で作ったような場所です。壁と壁でつながっているだけ。サルバドールって、一番寒くても22度とかなので、密閉していなくても生活することができる。志半ばで作ることをやめて、そこに住んでしまう。ここにいる20歳ぐらいの子も「小さい頃、僕もこの階段を作ったよ」って言っていました。この街は危険なところも多いけれど、ここにいるとなんとなく安全な感じがするんです。
会場:そもそも、なぜブラジルに行くのかという理由を知りたい。どこが一番共鳴するのですか?
永井:チューンされるんです。日本にいて狂うことが調整される。
会場:それは、アート、音楽、いろいろな断片があると思うけど、どのへんですか?
永井:全部。音も動きも視覚もすべて。たとえば太鼓の音とか、あの場所に行かないと聞くことができないクオリティがあるんです。上手な人も下手な人もいて、それを上手な人たちがひっぱっていってくれる。日々を過ごしていると頭だけで考えている自分がいるな、と思うんです。でも、そこには見えない何かに向かってひっぱっていってくれる感覚がある。言葉ではなくて、動物として調整される。
大西:永井さんの話を聞いていると、ブラジルの人なのかな?と思うときがある。憑依しているというか、自分のものになっていて、自分の言葉で話している。もし私が別の地域に行って、その場所のことが好きになっても、あくまでもよそ者に感じてしまって、自分のこととして言うことを遠慮してしまうことがある。(ブラジル人教育学者パウロ・)フレイレの本を読んでいると、それじゃだめだ、って言っているような気がするんです。相手に対して、本当に身を投げ出すぐらいではないと。
永井:日本だとパウロ・フレイレについてはこの本(「被抑圧者の教育学」)しか手がかりがなくって。でも、文字の書けない大人にたった3日間でどうやって読み書きを教えたのだろうと、不思議に思っていて、もっと実際的なことが知りたかった。それでレシフェに行くことにしたんです。レシフェはフレイレの故郷。それで現地に行って色々な人に話したら、私がもともと知っているアーティストが、フレイレについての作品を作っていることを知って。フレイレが実際にやったことは街のバーとか、人の集まる場所に行って、そこにいる人に話すこと。例えば、さとうきび畑での畑仕事を終わってくつろいでいる労働者と会話をする。身体どう?痛いところない?病院は?いくら払っているの?どちらの病院のほうがいい?とか、そういう会話をしながら。例えば、大人だったら薬という言葉はすでに知っているし、話せる。(すでに言葉を使う能力はある)でも書き方を知らないだけ。話している言葉に音節を当てはめていくと驚くほど早く習得できる。そもそも、60年代にブラジル全国で選挙をすることになって、国民全体を選挙に参加させるためには文字を読めなくてはならない、ということで、超特急で識字率をあげよ、という指令が政府から下り、そのときに教育省にいたフレイレがそのメソッドを編み出したということなんです。
会場:今は、押し合いヘしあいの状況のなかで、コミュニティが生まれていると思うのですが、例えば政府が譲歩して、要求を認めてくれることになったときに、いままで育まれてきたコミュニティはどうなるのでしょう?
永井:それはないと思います。政府が譲歩することはない。それは、現地の人とやりとりをしている感覚で感じます。でも、仮に彼らの主張の30%ぐらいを認めるということがあったとしたら、その30%を勝ち取ったことに全力で喜ぶ。それで残りの70%をまた全力で戦う。そういうことを、ちょっとずつやっているうちに人の寿命がきてしまって、その戦いを次の世代が引き継いでいくのです。だけど、その30%を勝ち取ったことの達成感とか勝利感は語り継がれる。
会場:貧しい人たちだけではなくて?
永井:確かに裕福な人たちもいるのだけど、すべては隣り合わせになっているんです。裕福な人も完全な社会ではないという事実を抱えて、ずっと問題を横目で見ながら一生を過ごしているわけですよね。見ようとしない人もいるけれど、逆にそういう人たちは恐怖感を抱えていて、自分の資産を守るために家をガチガチに壁で取り囲んだりします。そういう意味では誰もがずっと戦いつづけている。フレイレも亡命しなくてはならなかったし。
大西:ジンギさん(MTSCに参加しているアーティスト)はアーティストなので、いろんな社会に属しているのが印象的でした。あるオープニングパーティに連れて行ってくれたときは、あれ、街にこんな人が歩いてたっけ、みたいなスタイルがよくて美しい人たちばかりで。世界が違いました(笑)。
Photo: Musa Ding
永井:たまたまそういう作家に会っているのかもしれないのだけど、本人たちはそういう生活をしていることへのうしろめたさみたいのがあるような気がするんですよね。実際、貧しい家庭の出身だったアーティストもいます。だから積極的にファベーラに行ったりとか、小学校に教えにいったりとか、するんですよね。仕事のない人を雇ってあげたりとか。サンドラ・シントっていうアーティストがいて、彼女もブラジル人で、サンパウロでもとても大きな文化施設で展覧会をやるような有名な作家なんですけど。日本の人が彼女のアトリエに行くと、何人もお手伝いさんがいて、ドライバーがいて、なんて裕福な、って思うみたい。だけど彼女がよく言うのは仕事をシェアしているということ。彼らの健康保険を払ったり、自分たちが持っているものを確実に必要な人たちに分配しているんです。彼女のアトリエにいくとそれをすごく感じる。本人もそこまで高価なものを使ったりしない。そうやって分配しているという意識が強いですよね。
会場:印象深かったことは、永井さん自身がチューンされる、っていうところでした。実感がその言葉に出ている。日本で生活していて、私自身、それに代わるものはあるかな、と思うと悩ましいので、魅力的だなと思いました。問題を問題として認識したり、問題があるからみんなが団結してパワフルな状態が生まれる。問題に向かう力として音楽があって、音楽は言葉として、もしくは団結の手段として使われる。だけど、私自身、違和感があったのは、それ以上に快楽があるのではないかな、と。問題に対して、音楽を言葉の代わりとして使う。そこも日本の音楽の価値観というのが違うな、と。
永井:音楽は本当に気持ちがいいので、それを求めていってしまいます。ライブとか、そこにいるだけでいい。冒頭の(いろいろな音楽が連なる)動画はものの1日の出来事で。レシフェの近くのオリンダという街を歩いていたら、こうして全然違う音楽を奏でる人たちが練習している。でも、かつては辛い日々をすごしてきたひとたちがたくさんいたのだと思うんですよね。肉体労働で身体がぼろぼろだったり、主人から精神的に虐げられていたり。毎日がそういう生活だから、こういうところに行って自分が取り戻す。ブラジルにいって言葉がわかるようになると、歌の歌詞がすごく悲しいことを言っていることに気がつくんです。とても楽しい音楽なのに。「ご主人様にバターをこぼしたことを言わなくては」とか「壊れないと思っていた家が壊れた」とか。
意味がわかってくると、引き裂かれるような思いがします。例えば、奴隷にされたアフリカの人々は一切、帰ることを許されていない。3年に一回帰れるけど、それまで帰れないのが寂しい、のではなくて、故郷があることを知っているのに一生帰れないのです。何かができるまでの我慢じゃなくて、絶対実現されないものへの思い。だから、すごく強い意味。これがブラジル特有だと思うのは、ずっと引き裂かれるような心を持っている人の国、移民の国という社会背景があるんです。音楽は明るいのに、悲しい・・・、という二重性ですね。
会場:生きるために文化があるというのにハッとしました。文化を守るとか、いうことじゃない。会えない人に伝えるとか、次の世代のために言葉を残すとか、そういうことについての想像力を持っているんですね。
永井:ここでまとめたものって、美術館にはいらないものなんです。例えばヨーロッパみたいに、文化行政がしっかりとあるところって、必ず使わなくてはならない予算があったり、美術館があって、そのなかで展示するのが当たり前。お金は用意されているんです。だけど、そもそもそこに入らない文化がたくさんある。(ブラジルの路上の文化は)こんなに豊かなのに、美術館のなかでは同じように体感できない。この文化を続けるには、人を育てたり、人を介していかないといけない。私が今回まとめたものって、ブラジルのなかでも一部の文化なのですけど、ストリートにしかないものがここまで続いてきているということに、毎回すごく感動する。本当はそういうものって、どの国にもあると思うんです。建築とかやっていると、そういうものを意識しながら作ったりするのかな、と思ったりするのだけど。
大西:全体を通して永井さんの話を聞いて、最後に政治と社会運動というのがくるのだけど、最初は音楽からはじまったり、途中でレンガを作るシーンがあったり、何か感覚的なものとつながっている、というのが面白いと思いました。人間の間に共有されて言葉にならないものが変化していって論理的な社会運動になっていく。
永井:(ブラジルでは)みんな本当に大変なことも、そうでないこともよく話す。そうやって話すことが運動になっている。話し合いを続けながら、結果的に文化が形成されていくんです。例えば、目下の目的はここで音楽を引き続けるにはどうしたらいいか、というようなことだったりする。確かに、楽しい、とか、生きている感じがする、ということにみんなすごく敏感です。たとえばサンバの集まりをずっと続けていくにはどうしたらいいか考える。そのために場所を借りないといけないね、ということになる。制度はそのあとにできてくる。そういう身体の感覚は大切なんですね。
百田:お話を聞いていて「運動」っていうのが頭に浮かんで。ムーブメントという運動もそうだし、身体を動かすというのも。ムーブメントについては、あのocupacaoのプロジェクトもそうだけど、サポートする、されるの関係が曖昧になって、みな同じようなレベルで参加している。見方によっては福祉のプロジェクトに見えるけど、ムーブメントになった瞬間、もう福祉ではなくなる。それも面白いと思いました。あとインプットとアウトプットが一緒。受け身じゃなくて参加しているひとたち全員が感じて、発している。そう考えると、身体を動かす運動も音楽もムーブメントみたいな感じがする。日本で音楽といったらプレイヤーがいて聞くということが多い。でも(ブラジルの)音楽って、蓋をあけたらみんな参加できる、というような、すごい開放感がある。身体を動かしていると参加者になれる。それが感覚的な言語で、いろんな活動がムーブメントの原動力になる。
永井:まさに今回、私の旅をこのストーリーにまとめたこと自体に驚きと発見がありました。現地に行っているときは、必死でこの音を誰かに聴かせたいという思いで撮っている。この音楽がよすぎて、これをインスタにあげたい、とか。で、現地にいる人はみなこれが楽しくて、こういうことをずっとやっていたいからやっている。私もそれを振り返って、これがなんで起こったのかな、と考えてみると、これ自体がプロテストに見えたりする。振り返ると辻褄があっている気持ちになるけど、現場はこの断片でしかない。
会場:コロナで旅できなくなったじゃないですか。僕も奥会津みたいなところにいると、普段東京では使っていないような感性が開くことがある。そこから排除されてきた、この半年間は苦しい。だから、どうしているのかな、と思って。でも、今日聞いた話によると、かつての奴隷の人たちは数百年にわたってその感覚を経てきたわけでしょ。だからそこにヒントがありそう。生きるための文化じゃないけど、そういうことの産みの苦しみのなかに僕たちはいるのかもしれない。
(これはプレゼンテーションのあとに行われた会場の参加者との対話を後日編集したものです)
●当日の様子 / photo : Yurika KONO